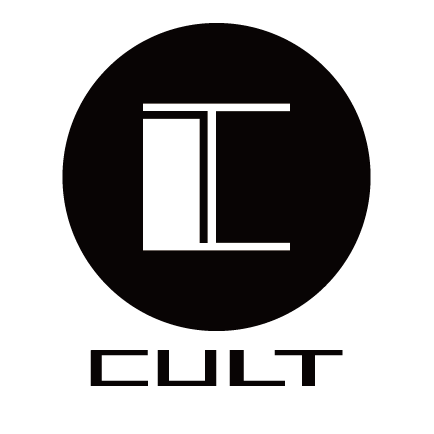スペシャルインタビュー 1:田村 進 (元日伸音波製作所)

言うならば、Maxonエフェクターの父。元日伸音波製作所の技術部にて、数々の名機を世に送り出したエンジニア、田村進氏に対する独占インタビュー。
- 2018年 8月 田村進氏の自宅にて -
-伝説のエンジニア、田村 進 -
ー 大変失礼ですが、現在のご年齢は?
田村 進(以下、TS):1953年4月29日生まれですので、現在65歳です(※2018年現在)。
ー 田村さん自身のバイオグラフィというか、どのような青年時代を送られて現在に至ったのかをお伺いできますか?
TS:私は(長野県の)松本で生まれて、松本で育ちました。工業高校を卒業したのですが、その時にアルバイトを2つしておりまして、1つは電話の交換局の工事。高校の時から電気に興味がありましたので、電話機の回路図、配線図があれば一通りのことは解りました。そしてもう1つは鰻屋さんです。一生分くらいの鰻を食べましたよ(笑)。
ー (笑)。工業高校ではどのような科目を専攻していたのですか?
TS:電子科です。5球スーパーとか、6球スーパー(※共に真空管式ラジオのこと)の製作実習なんかがありまして、私はアマチュア無線をやってましたので、送信機とか受信機とかも作ってましたから、ラジオなんてお手の物でしたよ。私が作ったそのラジオはその後、20年くらい手本として残されていたらしいですから。そして私は高校を卒業して、そのまま電話の工事屋さんになってしまったんですよ。日本中、色んなところに工事に行きましたね。
ー その会社に一度は就職された、ということでしょうか?
TS:知らず識らずのうちにそうなってしまっていましたね。しかし、その仕事で各地を回って家に帰れないことにも少し嫌になってしまっていた時、地元の松本で日伸音波(日伸音波製作所 = 自社ブランドとしてMaxonを保有し、Ibanezを始めとする数社のエフェクターもOEM生産していたメーカー)の専務と部長に声をかけられたんです。電話の工事や回路の設計をできるやつが近くに住んでるってことを聞きつけてね。それが「日伸音波に入ってくれない?」という誘いで。
ー それは田村さんがおいくつの時のお話ですか?
TS:21歳前後ですね。日伸音波は私の家のすぐ近くにありましたから、ギター関連の会社だということは知っていました。実は小学校の同級生にフジゲンの横内現会長の息子さんがいて、エレキギターを弾いていたことはありましたから。で、電話工事の会社を辞めて、日伸音波に連絡をしたら、「次の月曜から来てくれ」みたいなことになりまして(笑)。
ー つまり、それは何年のことになるのでしょうか?
TS:1974年の11月ですね。

ー 日伸音波製作所は1966年創業ですよね。その頃、日伸音波はどんな製品を作っていたのでしょうか?
TS:ギターのピックアップを作っていましたね。エフェクターはファズとワウがありました。
ー そこで田村さんが初めて手がけた仕事は何だったのでしょうか?
TS:ギターに直接挿すタイプのブースター、MB-10、20、30をご存知ですか?そのプリント基板の再設計が最初の仕事でしたね。プリント基板も趣味で作ってましたから、行ったらいきなりそれを任されましたよ。
ー その後、初めて設計されたエフェクターというのは?
TS:Phase Tone PT-999 というエフェクターですね。MXR Phase 90をしっかりと踏襲させて頂きました(笑)。
ー それは何年のことだったでしょうか?
TS:1975年だったと思います。おそらく星野楽器だったと思うのですが、アメリカから「今、こんなエフェクターが話題になってる」というようなことで、Phase 90が送られて来たんです。そのPhase 90はシングルOPアンプの741をいくつも使っていたのですが、OPアンプは当時としては非常に高価なものだったので、シングルの741を1つのデュアルOPアンプの1458にまとめて、コストを半減させて近い動作をさせました。
しかし、OPアンプの問題はまだ良い方で、本当に苦労したのはFETでしたね。位相を変える際に歪まないよう、かなりの数のFETを選別しましたよ。FETは同じ型番でもバラツキが多いので、選別の治具をわざわざ作ってね。さらに、FETを実装した基板側でも微調整ができるようにして発売したんです。そうしたら、えらい売れた(笑)。
ー なるほど(笑)

(1976年8月発行のカタログより抜粋)
TS:実はMXRが日本に入って来たのは、それから1年か2年後だったんですよ。だから、当時はMXRに対して、Maxonのコピー品が出て来たって言われてたんですよ。しかもコピー品の方が高いってね。
ー その頃、日伸音波は会社としてどんどん大きくなっていたのでしょうか?
TS:そうですね。ピックアップは多く作っていましたけど、やはりそれは1つの部品として捉われていましたから、オリジナルの電子回路を売っていきたいと考えていましたね。
ー PT-999が発売された当時、従業員はどれほどいたのでしょうか?
TS:ピックアップを作っていた人が殆どでしたが、30人くらいはいたんじゃないでしょうか。片方の生産ラインでピックアップを作って、もう片方でエフェクターを作っていましたね。エフェクターはかなり売れていましたよ。その当時、梯さんのところ(BOSS)とグヤ(Guyatone)とMaxonくらいしか流通していたものはありませんでしたから。昔はビルダーもいませんしね(笑)。
ー 田村さん以外にエフェクターを設計する技術者はいましたか?
TS:私が入った時はいませんでしたが、エフェクターを始めて順調に売り上げが伸びていったあと、Trio(Kenwoodの音響機器部門)から入ってきた人がいましたね。一部のモデルはその彼が担当していました。
ー 具体的にはどのモデルでしょうか?
TS:フェイザーでPT-707 ってありましたよね。それとかですね。
ー なるほど。逆に、それ以外のモデルは全て田村さんの設計ですか?
TS:入ったばかりの頃は全てやってましたし、70年代から80年代の始め頃までのものでしたら、半分以上は私です。関数電卓を使って、手書きで回路図を書いて試作して、何か不具合があれば回路図に赤を着けて直して。当時は作ったら売れる時代だから、楽しかったですよ。
ー 具体的に、PT-999から始まる、あの小型の筐体のシリーズは全て田村さんの仕事でしょうか?
TS:全てそうでしょうね。
ー Flying Panなどのシリーズは?
TS:Flying Panはやってないですね。同じシリーズのJetlyzerはやりました。9シリーズのあとはアナログにはあまり関与しなくなり、ラックやゼロワン(01)シリーズでデジタルものを全部やってましたよ。カスタムICのデザインから全てです。あとは、面白いものだとMaxonのオリジナル9V電池のデザインもやりましたね。
ー 電池までも!
TS:まぁ、外装だけですけどね。

(1977年発行のカタログより抜粋)
ー ちなみに、エフェクターの色なんかも田村さんが決めてたんですか?
TS:色も決めてましたね。例えば、PT-999 はPhase 90を見て、そのままオレンジ色に。ただ、それ以降は割とその時々でしたね。それぞれが近い色だと間違ってしまいますから、フランジャーは黄色でいこうとか、ディレイはピンクにしようとか、そんな調子です。型番だってそうですよ。
ー 歪みは緑系の色ですよね。
TS:そうですね。一番最初のよく歪むD&Sは濃い緑、ちょっと歪みが少ないD&S II は薄い緑、SD-9(Sonic Distortion)も薄い緑ですよね。
 (1980年11月発行のカタログより抜粋)
(1980年11月発行のカタログより抜粋)
-1978年、名機OD-808の誕生-

▲2台のOD-808。写真右は1979年製、左はマイナーチェンジ直後の1980年製。両者ではイン/アウト・バッファー部分の回路が異なる。
ー では、名機と誉れ高いOD-808についても聞かせてください。まず、OD-808を作ろうとしたキッカケはどのようなものだったのでしょうか?
TS:歪みエフェクターの中で、まずファズやディストーションが売れていたのですが、その当時の音楽があまり歪ませない方向へ変化していた。アンプのようなオーバードライブというものに需要があったんでしょうね。で、そんなに歪まない歪みエフェクターが必要となって、作ったんですね。
私の作ったオーバードライブでいうと、OD-880(Soft Distortion)ってのが一番最初だったんですよ。あれは、増幅回路の後にクランパーがパッシブで付いてる。積分を1回してもう1回積分をすると、正弦波が三角波になって、三角波がまた正弦波に戻るんですよ、基本的にね。その三角波になった部分をダイオードで歪ませると、ちょっと歪んでくれる。そんな発想でした。
ー それがあまり歪ませないようにするための最初の手段であったと?
TS:いや、実はそれは真空管の歪みを再現しようとしたんです。それもプリアンプではなく、パワーアンプの五極管の歪みですね。半導体だとしっかりとクリップしてしまって、少し耳障りじゃないですか。それと違って柔らかい歪みが欲しかったということです。

▲写真左は1979年製のOD-808、右は1977年製のOD-880。OD-880はより円やかな音色を持つ。
ー それはいつのことでしょうか?
TS:1976〜77年のことだったと思います。そのOD-880も当時としては結構売れて、前振りが長くなってしまいましたが、そのあとにOD-808を作るわけです。(先に発売されていたBOSSの)OD-1を参考にしたかどうかと聞かれることもありますが、実はOD-808を作る上で一番大きなヒントになったのは、OPアンプの応用回路図集のような本にあったアナログ乗算機/除算機の回路です。それがOD-808の負帰還にダイオードを入れた使い方のヒントの1番の元になったんです。OD-1も知ってはいたと思いますが、回路まではチェックしていませんでしたね。
ー 乗算機の回路とは、意外ですね。音色としてはどのようなものを狙っていたのでしょうか?
TS:正直なところ、当時としてはよく解らなかったのですが、今思えばチューブアンプをドライブさせるもの、今でいうブースターのようなものを作りたかったのだと思います。低域が出ると暴れるし、高域が出るとMarshallのアンプなんかは耳に痛いし、そうしてあの中域が盛り上がった特性になったんです。
ー あのカマボコ型の周波数特性は、やはり狙って作られていたんですね。製品化にあたり、細かな調整などを繰り返して、あの音色、特性に着地したのでしょうか?
TS:いや、そんなにしてなかったと思います。ただ、製品として出す前に国内の著名なギタリストにテストをしてもらいましたし、アメリカでも持ち回り、それでOKが出たから発売したのは間違いないですね。
ー ということは、試作前から完全に狙ったヴィションがあり、それが当たっていたということでしょうか?
TS:6弦の開放が81Hzで、1弦のかなり高い方の音で1,048Hzか何かなんですよ。その帯域がファンダメンタルになるということは解っていたので、基本的にはその中間にピークを作ったらあの特性になったんです。必要ないと思われるところを切った、という感じですよ。実は私はコードすらも知りませんでしたから、倍音に関してや音楽理論に関してはかなり勉強しましたよ。
ー そうだったんですね。OD-808を設計されたのは何年のことでしょうか?
TS:1978年だったと思います。OD-808は1978年11月の楽器フェアで発表したと記憶しています。

▲どちらも1980年製のTS-808とOD-808。TS-808は日本国外で流通し、OD-808は日本国内で流通していたため、当時は両者が一堂に会すことは珍しかった。
ー その翌年、1979年のNAMM showでIbanez TS-808が発表されたと聞いています。Ibanezと日伸音波はどのような関係性だったのでしょうか?
TS:私が入る以前から、国内の卸問屋は神田商会、国外は星野楽器(Ibanez)と決まってましたから、特に深く考えることもなかったですね。ちなみに、その当時はディストーションやファズをサスティナーと呼ぶことが一般的だったんですよ。しかし、それをIbanezはあまり良しとしておらず、(実際はファズである)OD-850 をOverdrive、(実際はディストーションである)OD-855 はOverdrive II として発売していましたね。しかし、さすがにOverdriveが3までいくと少しややこしいとなり(笑)、新たなネーミングを探していたわけですよ。
その前後、ニューヨークで何かの試作機を持ち回っていた時に、Sam Ashの社長の息子の一人であるSummyが「Crybabyってどんな意味か知ってるか?」と訊いてきて、「もちろん、知ってるよ」と答えると、何かを弾きながら「これはTube Screamerだ!」なんて言ったんですよ。その時に持ち回っていた試作機が何だったのか、OD-808 だったのか、はたまたGA-10(Micro Teacher = エフェクターサイズのミニアンプ)だったのかは覚えていませんが、その時に聞いたTube Screamerという単語をIbanezが製品名として採用したんです。
ー そうだったんですね。
TS:また、当初のMaxonの筐体はMXRと非常に似ていたので、アメリカで販売するにはスラント・ノーズ形の筐体にしようとIbanezが提案して、あの筐体となったんですよ。先に出ていたPhase Toneとかもそうですよね。
ー 結果、発売されたOD-808はその当時も好評でしたか?
TS:いや、D&Sシリーズの方が売れていたと思いますね。しっかりは調べていませんが、特にD&S II です。あと、その後継機種のSD-9 ですね。ちょっと回路が変わっていて、ドンズバではないのですが、SD-9 はD&S II の後継だったんですよ。OD-808、OD-9 は80年代にSRVが亡くなられてから人気が出始めたのが正直のところです。

▲写真左が1980年製のOD-808、右は1983年製のOD-9。
ー そのOD-808からOD-9へモデルチェンジをした際、内部の回路の定数が2箇所だけ変わっています。それが世界中で様々な憶測を呼んでいるわけですが、なぜ、そのような変更を施したのでしょうか?
TS:出力部分のバッファーにトランジスタのエミッターフォロワという回路を使っているんですが、OD-808ではそのトランジスタに付いている抵抗が10KΩなんですね。それが一般的には低過ぎるということで、10倍にした100KΩに変更しました。また、静電気などに対する保護の目的で入っている100Ωをより効果的な470Ωに替えています。
ー その当時、静電気対策は必要なことだったのでしょうか?
TS:松本って内陸性の気候だから、それなりには空気が乾いてるんですよ。だけど、アメリカの方がもっと空気が乾いていて、静電気が起きやすかったんですね。今と違って、床に敷く絨毯も帯電防止のものは少なかったですし。その静電気でアメリカに出荷したエフェクターが壊れることがあったんですよ。そういった静電破壊が起きる場合、入力か出力か電源が壊れるんですよ。でも、電源は結構強い。そうなると入力か出力ですが、それが先ほど申し上げた部分です。

▲ 写真の向かって左がOD-808、右がOD-9のそれぞれ基板部。使われているパーツに多少の違いはあるが、両者にはほぼ同様の基板、回路が使われている。回路上での違いはわずか2箇所の抵抗値のみ。
TS:でもね、どっちの回路でも測定するとちゃんと意図した特性が出てるんですよ。
そもそも、その抵抗値の差で音が変わると思います?
ー 個人的にOD-9を808の定数に変えた経験はありますが、ほとんど変わらないと思いますね。ただし、ヴィンテージのOD-808とOD-9を比べると、それぞれで違う音の傾向があるとは思います。
TS:まぁ、大成に影響はないですよ。ただし、理論的にはアンプのインピーダンスが極端に低いようならOD-808の定数ではレベルが下がる可能性はありますが。ただね、実は9シリーズは苦労したんですよ。というのも、フットスイッチの下にバネが入っているんですけど、そのバネの設計が本当に難しかった。バネの巻ピッチ、段数なんかを計算して作っても、計算通りには全然ならなかった。あと、電池蓋の設計もそう。樹脂の弾性の計算も難しかった。餅は餅屋ですね。筐体の設計なんかはまだ良いですけど、機構部品は難しいですね。
ー なんと、田村氏は回路だけでなく、筐体、電池の蓋、さらにはバネ1つに至るまでまで自身で設計していた。
-CULT TS808 #1 Cloning mod.について-

- CULT TS808 #1 Cloning mod.についてはコチラから -
ー 今回、クローンする対象とした1980年製のTS-808、通称"Sample #1"。どのような点をどのようにすれば、クローンが完成すると考えましたか?
TS:ヒアリングでピッタリ合って、測定器でも裏付けが取れた時、それが完成だと思います。もし、そのどちらかが欠けるようなら、何らかの理由が必ずある。何を計測して、どのパラメーターをどうすれば良いか、それは長年やってきた経験からですね。今回は3ヶ月以上もの長期間に渡って測定と分析をしましたから、それが勝因でしょう。

ー 最も苦労した点はどんなことだったでしょうか?
TS:一番は "Sample #1" の部品を取り外せないことですね。部品を取り外して、個々の特性を測定、解析できたとすれば、もっと早く完成していたと思います。日伸音波に勤めていた時代を含めても、これほどまでに時間をかけて精密な解析を繰り返し行ったことはありません。
また、モディファイというと、スイッチの追加や基板裏面パターンのカットなんて方法もありますが、そういったことはなるべくしたくない。追加工が元々の製品の信頼性を落としかねないですから。ですので、そういった加工をせず、目的の音に到達しなければならない。それも大変なことですね。
ー 逆に、回路を変更して何かの特性を再現することは、さほど難しくなかったということでしょうか?
TS:そうですね。それは、ずっとやってきたことですから。
ー この回答をそのまま載せてしまうと、田村さんに様々なクローン依頼が殺到してしまいそうですね。
TS:確かにそうかもしれませんね。ただ、SRVの TS-808 でもない限りはやりませんよ。作業自体は楽しかったですけどね。
ー 今回のようにクローンを作り上げる方法の中でも、特に重要なことはなんでしょうか?
TS:くどいようですが、測定器で見て、数値を合わせることです。あくまでも。
-田村氏が手がけたTS808 #1 Cloning mod.についてはコチラから -
次の投稿 →